毎日子育てや家事でバタバタの中、気づいたら1週間前からずっと頭痛が続いている・・・ということありませんか?
実は子育て中のママが抱えがちな体調不良の一つとして慢性的な頭痛があります。軽い頭痛なら一時的なものと思って放っておきがちですが、きちんと対処しないと治りにくくなってしまう可能性があるので注意が必要なんです。


目次
頭痛の原因

頭痛が起こるメカニズム
一言で頭痛と言っても原因は様々で、自分で対処できるものからきちんとした治療が必要なものもあります。まず頭痛が起こるメカニズムについて簡単に解説していきます。
何らかの原因で組織がダメージを受けると、それを修復しようとする過程で細胞からプロスタグランジンという物質が生成されます。このプロスタグランジンが組織の炎症を引き起こし、その結果痛みや腫れ・発熱などの症状が起こります。
頭痛の場合は脳血管の拡張や外からの刺激によって脳細胞でこの反応が起きている状態と言えます。市販の頭痛薬はこのプロスタグランジンの生成を抑える成分が含まれいているものも多いです。
頭痛にはいわゆる一般的な頭痛である一次性頭痛と、病気が原因となって起こっている二次性頭痛があります。症状によっては病院で治療を受ける必要がある場合もあるので、まずは自分の頭痛のタイプをしっかり判断することが必要です。

一次性頭痛

一般的に「頭痛持ち」などと言われる単純な頭痛です。片頭痛や緊張型の頭痛など、基礎的な疾患がないにも関わらず起こる頭痛がこれに当てはまります。
一般的に起こりやすい頭痛の型について、原因と症状をまとめました。
原因
脳の一部の血管が拡張することでその周囲の神経が刺激されて起こる頭痛。ホルモンバランスの変化や疲労などが発症要因となる。
症状
左右どちらかのこめかみから目の周辺にかけてのズキズキとした脈打つような痛み。頭痛以外に吐き気などを伴う場合もある。気圧や天候によって悪化することもある。
原因
頭・肩・背中の筋肉の緊張によって起こる。筋肉の緊張が続くことで血流が悪くなり、老廃物が貯留して神経が刺激されることが原因。
症状
後頭部を中心に締め付けられるような痛み。目の疲れや疲労感を伴う場合もある。痛みの程度は比較的軽いが慢性的に続きやすい。

二次性頭痛

身体に何らかの異常や疾患があり、その結果として起こる頭痛です。この場合は病院で元となる病気をきちんと治療する必要があります。
- くも膜下出血
- 脳出血
- 慢性硬膜外血腫
- 髄膜炎などの感染症
- 脳動脈解離
いずれも脳の病気や頭に起こる異常が原因になっているので早期の病院受診・治療が必要な状態です。
これらは急激に頭痛などの症状が出現するので比較的異常に気付きやすいです。しかし、慢性硬膜外血腫は頭をぶつけるなど頭部に衝撃を受けた後にじわじわと頭の中で血腫(血の塊り)が広がるので数日後に症状が起こる場合が多く注意が必要です。

注意しなければいけない症状

脳の病気など、特に注意しなければならない病気の症状として起こる頭痛の特徴をまとめます。これらの症状が出た場合は危険サインなので注意しましょう。
- 急激な激しい頭痛(打たれたような、今まで経験したことがないほど)
- 吐き気や嘔吐を伴う
- 手足の痺れや動かしにくさを伴う
- 呂律が回らない、感覚や味覚の異常
- 視野障害(目の霞みや視界が狭くなるなど)
一次性の頭痛は症状が良くなったり悪くなったりと波があったりします。一方でこうした病気がベースにある場合は数時間〜数日で急激に症状が進行することが多いです。
また、高血圧などの生活習慣病など、他にも頭痛を引き起こす病気は多くあります。薬の副作用などでも頭痛が起こることがあります。不安な時は専門家に相談するようにしましょう。
子育て中に起こりやすい頭痛はどんなもの?

子育て中に起こりやすい頭痛

子育て中に起こりやすい頭痛は一次性頭痛の中でも緊張性頭痛が多いと言われています。
お子さんが小さい間は、抱っこや寝かし付けなどで長時間同じ体勢を取ることが多くなりがちです。また飲み物やお菓子、着替えなど何かと荷物が多く、重いカバンを持ち歩く必要がありますよね。このような積み重ねで身体に負担がかかり、肩や首の凝りが頭痛の原因になります。
一方、子育てのストレスや疲労、無理な生活によるホルモンバランスの乱れから頭痛を起こしやすくなる場合もあります。
ストレスや疲労が原因の頭痛は片頭痛が多いですが、慢性的にストレスや疲労を抱えていると無意識のうちに身体の負担がかかり、緊張性頭痛を引き起こすこともあります。
お子さんのペースに合わせた生活になって自身の生活リズムが乱れている、睡眠不足や栄養バランスの偏りがあるという方も多いと思います。睡眠や食生活が乱れると自律神経やホルモンバランスが崩れ、片頭痛の原因になってしまいます。


子育て中の頭痛の対処方法
緊張性頭痛と片頭痛では対処の方法が違います。間違った方法だと症状を悪化させる可能性があるので注意しましょう。
- 肩〜首の血行を良くする:マッサージやストレッチをする、蒸しタオルで肩や目を暖める
- 休憩を取ったり、気分転換をしてリラックスする
- 血管を収縮させる
(頭や目など痛む場所を冷やす、カフェインの入った飲み物を摂る) - 光や騒音を避け、安静にして休む
また、片頭痛の場合はチョコレートや赤ワイン、ヨーグルトなどの発酵食品は症状を誘発する可能性があると言われています。症状がある時には控えるようにしましょう。
症状が起こった時に対処することも大切ですが、頭痛を日頃から予防し慢性化しないようにすることが重要です。
また、自身の症状(頭痛がどんな時に出現するか、痛みの程度、どのくらいの時間続くかなど)を自分自身で観察・記録して、頭痛が起こりやすい環境や時間帯、天候などの傾向を見ておくと予防がしやすいです。
慢性化する前に!生活習慣に取り入れたい予防方法

ホルモンバランスを整える

自律神経やホルモンバランスの乱れが原因の片頭痛に対しては、その乱れを整えるような生活習慣を取り入れることが必要です。
自律神経やホルモンバランスには食生活や睡眠、ストレスが密に関わっています。普段お子さん中心の生活で自分の睡眠時間や食生活が乱れているという場合はこの辺りを少しでも解消できるよう心がけてみましょう。
十分な睡眠時間をとることが難しいという場合でも、毎日決まった時間に寝起きするだけでも体内のバランスを整えることができます。

また、睡眠の質を上げられるよう就寝前にミルクやハーブティーを飲んでみる、寝る前にスマホを触らないなどの習慣を取り入れてみるのも効果的です。
常にストレスが溜まっている、緊張状態が続いているという場合は意識的にストレス解消する時間を取ることが必要不可欠です。短時間でも家事や育児から離れてリラックスしたり、自分の好きなことをする時間を取り入れてみて下さい。
ストレス解消については子育てや家事に疲れたら試す価値あり!所要時間別、気分転換法27選や「子育てで疲れが取れない!」そんな育児から抜け出す方法をご覧になってみてください。
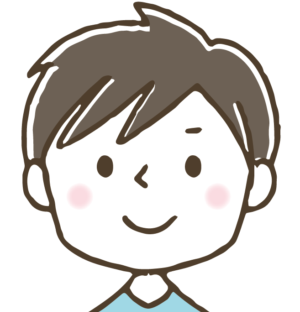

筋肉をほぐして血流を良くする

子育てで長時間同じ姿勢を続けたり、背中や肩など同一部位に負担がかかり続けることが多くなることで起こる緊張性頭痛の予防には、筋肉の凝りや疲労を放置せずに解消することが必要です。
短時間でもストレッチやマッサージをしてできるだけ凝りをほぐすようにしましょう。肩や背中、首の緊張や凝りをほぐすものが効果的です。
こちらの動画は短時間で手軽にできるのでオススメです。

こうしたストレッチはすぐに劇的な効果が出ないこともあります。自分が気持ち良いと感じるものや取り入れやすいものを1ヶ月程度は続けてみましょう。健康的な習慣を取り入れているというだけでも気分が前向きになる効果もあります。
また、肩周りの血流を悪化させないためには「カバンをリュックタイプにする」「肩がけの場合は交互に持つ」ようにして負担を軽減しましょう。暖かい飲み物を飲んだり湯船に浸かるなどで体を冷やさないことも効果的です。

市販薬を使う時は注意が必要

市販の頭痛薬は症状がひどい場合には使っても問題ないでしょう。使い過ぎると副作用が出る場合があるので、もちろん用法や用量をしっかり守ることが大切です。
また、薬はあくまでも症状を抑えたり緩和するためのもので、根本的な治療にはならないという点には注意が必要です。
ここまでの記事を参考に普段の生活から頭痛の原因となっているものを探り、少しでも改善できるよう心がけてみて下さい。
まとめ

- 頭痛には一次性頭痛と二次性頭痛があり、タイプを見極めることが必要
- 子育て中の頭痛は自律神経の乱れやストレス、肩こり・筋肉の緊張が原因の場合が多い
- 自律神経やホルモンバランスを整える生活を意識することが必要
- 市販薬は根本的な解決にはならない点に注意
毎日元気に育児や家事をするためにも、ツラい頭痛はできるだけ早く治したいですよね。
頭痛は毎日の疲労やストレスが溜まっているサインとも言えます。さらに、放置して慢性化すると、将来血管を痛めてしまう要因にもなってしまいます。
原因を見極めて早いうちにしっかり対処していきましょう!

























