弁当は外食のランチと比較すると食費の節約にもなり、健康を維持するためにも、毎日食べたいとは思います。でも朝は忙しく、手間がかかるし、何しろ面倒です。
でも、少しの工夫で弁当作りがとても楽になる方法があります。それは作り置き。特におかずを作り置きすると非常に時短で弁当が作れます。
今回はお弁当のおかずを作り置きして忙しい朝でも簡単にできるコツを紹介したいと思います。
目次
弁当を作るメリット・デメリット








お弁当は作りたいとは思っていますが、どうしても「面倒」というイメージが先行しがちです。でもお弁当を作るのはこんな嬉しいメリットがあります。
- 栄養バランスがよくヘルシー
- ランチ代が節約できる
- ランチの混雑時に並ばずすぐに食べられる
- 添加物がない又は少ない
- 食品ロスを少なくする
弁当のおかずは量と内容を自分で調節できます。それに決められた昼休み時間も無駄に過ごすことなく、効率的に休憩がとれしかも今までかかっていたランチ代の節約にもなります。
更に手作りのおかずなら添加物も極力避けることができ、夕飯などのおかずを利用、アレンジすることにより食品ロスを防げることができます。
しかし1からの弁当作りは大変です。
- 朝は忙しく作る時間がない
- メニューを考えるのが面倒
- 弁当箱を洗うのが手間
朝は1日の中で最も忙しい時間帯。その時間に更にお弁当作りに時間を費やす分、早起きも必要になってきます。また夕飯同様、おかずのメニューを考えるとなると更に手間がかかります。また、旦那様の帰宅が遅いと弁当箱が汚く不潔なままで、更にそれを防ぐには遅い帰宅時間まで待っていなくてはなりません。
そこで、お弁当のおかず作りでとっておきの便利な方法が作り置き。おかずの作り置きをすることによって弁当を作るメリットを生かし、デメリットを解消してくれます。でもそこにはちょっとした工夫とコツがあるのです。
では、詳しくみていきましょう。
弁当のおかずを作り置きするコツと注意点とは?

弁当のおかずを作り置きするためのコツを知ると作業がとても効率的且つ時短に繋がります。また作り置きをする際に注意しておかなければならないことがあります。ではどんなコツと注意点があるのでしょう?
- ついで調理で弁当作りの時間を短縮
- ほったらかし調理で作業効率アップ
- 汁気の多いおかずに注意
- 保存期間をわかるようにしておく
- 持参する弁当のおかずは毎回3品位を目安に
- 簡単おかずで持続性をキープ
ついで調理で弁当のおかず作りを短縮
ついで調理とは
- 夕食を作るついで
- 休日のごはんの支度をするついで
など、調理作業のついでに弁当のおかずを作ってしまうことです。例えば「ひじきの煮物」が夕飯のおかずならば、少し多めに作っておいて弁当のおかずの1品にしてしまうと朝時間が短縮されますよね。食事の準備時に常に「弁当のおかず」を意識しておくと「ついで調理」が楽になります。
ほったらかし調理で作業効率アップ
作り置きおかずをその日利用する場合は、とにかく作業や調理工程が簡単なものが楽。詰めるだけ、レンジで解凍するだけ、トースターで焼くだけなど、簡単な作業又は調理器具に調理をおまかせにして、その間に同時進行で別の作業できることによって効率をアップさせることができます。忙しい朝には大事なことです。
汁気の多いおかずには注意
煮物やゆで野菜などの汁気の多い作り置きおかずは、いざお弁当を食べようとした時、全体に汁が行きわたり味や見た目が変わってしまい、さらに漏れた汁が荷物に付いてシミや臭いの原因になる可能性があります。
そんな場合は、例えばほうれん草のお浸しなら、おかずカップにかつおぶしやすりごまを予め多めに敷き詰めておくと素材の水分を吸収してくれるので、汁漏れを防げます。また密閉できる弁当箱を利用するのも汁漏れ対策には有効です。
保存期間をわかるようにしておく
作り置きおかずは予めおかずを作っておくことが基本なため、保存期間をしっかり確認できることが大切です。特に夏場のお弁当は食中毒が心配です。そのためには作成日を明記しておくとわかりやすいでしょう。
その際にキッチンに白いマスキングテープと油性ペンを用意しておき、日付をマスキングテープに記入し容器や袋に貼り付けておくと、作成日がわかりやすくまた、作り置きおかずが無くなって容器を洗う際に剥がせば繰り返し使えるので便利です。
持参する弁当のおかずは毎回3品位が目安
弁当のおかずを作り置きしても、大量に作ると食品ロスや保存性に問題があります。持参する弁当のおかず数は3品位を目安に作り置きをしましょう。
さらにステップアップとして彩りを「赤・緑・黄」を意識すると見栄えのいいお弁用に仕上がります。
簡単おかずで持続性をキープ
最初から凝ったおかずを作るとハードルが一気に上がります。すると作業時間も増えるので、毎日のモチベーションが下がり持続性も低下します。まずは自分ができそうな所から挑戦し、無理をせず、簡単なおかずを作る、週1日位から徐々に弁当持参の日を増やすなど気軽な気持ちで弁当作りをしましょう。
栄養バランスを考えた常備野菜を作ろう

お弁当のおかずの栄養バランスを考えた場合、やはり野菜は必ず入れたいメニューです。そんな時は作り置きの常備野菜が便利です。しかし野菜のおかずは下ごしらえが重要ですが、忙しい朝にするのは至難の業。
そこで簡単な方法で下ごしらえを済ませて作り置きをしておくと、煩わしさを感じません。ではどのように下ごしらえをすればよいでしょうか?
レンジで蒸し野菜
お弁当の野菜でよく使われるのが緑黄色野菜。最近ではシリコンスチーマーのようなレンジ調理対応器具がありますよね。こちらを利用してほうれん草、もやし、人参、じゃがいも、オクラ、かぼちゃなどをレンジで蒸しておきます。
レンジ蒸しは茹でる調理もよりも簡単で、更に栄養成分の損失が少ないのが大きな特徴です。レンジを上手に活用して蒸し野菜を作っておきましょう。
多めに野菜をカット
朝の忙しい時間はできるだけ洗い物は減らしたいもの。ですから包丁やまな板はなるべく使いたくないわけです。そのため、野菜をカットするのは夕飯時などに多めにカットしておいて、朝は炒めるだけ、弁当に詰めるだけにしておくととても楽です。
漬けておくだけ野菜
トマトやきゅうり、大根、人参など時間がある時に多めに浅漬けやピクルスを作っておくと弁当のおかずの1品になります。漬物がお弁当に入っているとごはんも美味しく食べられます。またピクルスは酢を使っているので酸性作用で保存効果もあります。もちろん朝夕のおかずとしても利用できます。
炊飯器を利用
じゃがいもやさつまいもを蒸かすのは時間がかかりますが、ご飯を炊くついでに炊飯器でじゃがいもやさつまいもを入れておくと「蒸かし芋」が出来上がり、ポテトサラダ等にする時に便利です。
ポイントはイモ類はよく洗い、皮のままアルミホイルに包んでおくと衛生的です。面倒なポテトサラダもとても楽にできますよ。
一度に茹でてしまう
いんげんやアスパラガスなどのゆで野菜は大きめの鍋で小さいざるなどを利用して一度に茹でてしまうと常備野菜を作る作業効率がアップします。
簡単且つついで調理でできた常備野菜は密封容器に入れて冷蔵・冷凍保存しておきましょう。保存期間は野菜にもよりますが冷蔵の場合2日位・冷凍の場合2週間を目安に保存しましょう。変色や異臭がある場合にはすぐに廃棄しましょう。
作り置きおかずを冷凍しよう

作り置きおかずを作っても保存期間が短いと作り過ぎて食品ロスになったり、また常に弁当のおかずを作るという手間がかかります。その対策として作り置きおかずを冷凍することをすすめします。
冷凍おかずであれば、保存性も高く、そのまま詰めるだけなら夏場での食中毒のリスクも低くなります。では弁当の作り置きおかずを上手に冷凍、利用する方法を紹介します。
冷凍耐性のある常備菜を作ろう
冷凍耐性のない常備菜は、お弁当を食べる時、食感が悪く水っぽくなり、風味も落ちて美味しくありません。特にレタスなどの水分の多い生野菜は水っぽくなるので冷凍には向きません。また茹で卵も食感が悪くなるので冷凍には向いてないので注意しましょう。
繊維質のごぼうやレンコンはきんぴらなど加熱調理をすることによって、冷凍できるおかずになりますので、素材を調理加工したおかずは冷凍には向いています。
密閉容器に入れて空気に触れないようにする
冷凍作り置きおかずは空気に触れると酸化や霜が付きやすく「冷凍やけ」といわれる現象を起こし味、風味を低下させます。
作り置きおかずを冷凍する場合、庫内で一定温度にする、空気に触れないようにするために密閉容器や密閉袋を平らに均一になるように冷凍させるのがコツ。また保存期間もおかずにもよりますが1か月までには食べきるようにしましょう。
半調理品品・全調理品品
冷凍作り置きおかずは半調理品と全調理品の作り置きをしておくと非常に便利です。
半調理品
鳥そぼろ・トマトソース・ゆで野菜・調味液に浸けておいた薄切り肉、衣づけのコロッケなどを密閉袋に冷凍しておくとマンネリ化したお弁当のおかずをいつもと違うアレンジでリメイクできます。
例えば、ゆでたほうれん草は胡麻和えが定番ですが、チーズをトッピングしてトースターで焼けばほうれん草のチーズ焼きができます。トマトソースを解凍し、ひき肉と炒めてごはんにトッピングすればミートソース丼としてのっけ弁当が手軽にできます。
味のアレンジが効くので弁当のおかずはもちろん、朝夕飯のおかずにもなり時短にも繋がりまた、料理のレパートリーも広がります。
全調理品
ハンバーグやシュウマイのような全調理工程が完了している調理品は、お弁当の利用する際に詰めるだけ、レンジ解凍するだけなど簡単に利用できるので便利です。
またひじき煮などの全調理品でも、そのままお弁当のおかずとして詰められますが、卵焼きの中に入れたり、ひじきご飯にするなどリメイクして利用することができるので便利です。
冷凍作り置きおかずを上手に解凍して時短弁当を作ろう

冷凍した作り置きおかずを上手に簡単に解凍させて、美味しい時短弁当を作る方法を紹介します。
自然解凍
きんぴらやひじきの煮物などは予めおかずカップに入れて冷凍しておくと、そのまま弁当につめるだけで、お弁当を食べる時には程よく解凍されて美味しく食べられます。
おかずカップは100円ショップで購入でき、紙製、アルミ製、シリコン製の素材があり、使い捨てなら紙製とアルミ製、洗って再度使うならシリコン製と用途に分けて使用すると便利です。
レンジ解凍
500Wや600Wのレンジで作り置きしたハンバーグやグラタンなど短時間で解凍するときに便利です。またおかずカップで作り置きしている場合は、紙製、シリコン製を使い、アルミ製の場合はレンジ内でスパークする可能性があるので注意しましょう。
トースター解凍
おかずに焦げ目などを付けて見栄えよくするにはトースター解凍がおすすめです。やや解凍に時間がかかったり、焦げ過ぎないように気を付けましょう。
炒め解凍
お弁当用フライパンは2、3区分に分かれて同時調理が可能なため、一遍に2~3品のおかずができるのが便利です。もちろん普通の大きめのフライパンでも同時調理は可能です。
例えば、作り置きした冷凍野菜をソテーしながらウインナーを炒める時などはあっという間に2品できますよね。
違う解凍方法の合わせ技で素早く弁当のおかずを作りましょう。
作り置きおかずを弁当箱に詰めて冷凍しちゃおう!





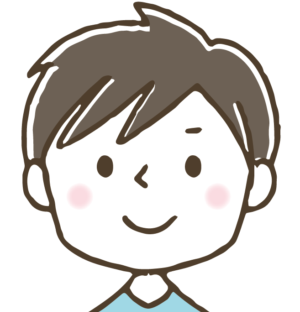

こんなシチュエーションの場合、大変ですがやはり旦那様にはお弁当を作ってあげたいですよね。でも冷凍作り置きおかずがあれば、楽にできる方法があります。
それは冷凍しておいた作り置きおかずを弁当箱に詰めて冷凍保管しておくだけ。では手順を詳しく紹介します。
- 前日に冷凍しても大丈夫な弁当箱(出来れば仕切りがあるもの)を用意する
- 冷凍作り置きおかずを弁当箱のおかず部分に隙間なく詰める
- 2にそのままふたをして弁当箱ごと冷凍庫で保管
- ごはんは早めに炊き上がるようにタイマーをセット
- 箸や小分けふりかけなどを旦那様にわかるように準備しておく
- 翌朝、作り置きおかずの入った弁当箱を冷凍庫から旦那様に取り出してもらう
- 旦那様にごはんだけ詰めてもらい、ふたをすれば完成
特に夏場などは前日に作っておくと食中毒の恐れもありますが、おかずが冷凍されていればある程度の保冷効果もあり、ごはんも当日詰めるので食中毒のリスクも低くなります。また、簡単な作業であれば旦那様も協力することができます。
早朝や忙しい朝でも前日の準備次第で美味しいお弁当が作れます。また、職場などでお弁当を食べる場所や給湯室などに電子レンジがあればご飯を冷凍、解凍しても、温かいお弁当が食べられます。その場合はある程度の密閉できるお弁当箱は数個必要ですが1週間分のお弁当を作ってしまうことも可能です。
自家製冷凍弁当を準備できればさらに朝時間に余裕が生まれます。アイディア次第で冷凍作り置きおかずがあればとても便利に利用でき、毎日の生活に余裕が生まれますよね。



まとめ

作り置きおかずを利用したお弁当作りはいかがでしたか?では弁当のおかずを作り置きするポイントをおさらいしましょう。
- 簡単な作り置き弁当おかずから始めて持続性を保つ
- ”ついで調理”で作り置きおかずの手間を削減
- ”冷凍作り置きおかず”で保存性と作業性をアップ
- 解凍方法は簡単な工程と合わせ解凍技で時短弁当
- 詰めた弁当を弁当箱ごと冷凍保存し、数日分の弁当を作り置き
最初は「面倒」だった弁当作りもやってみると意外と簡単にできることを実感できたでしょうか?これを機会に作り置きおかず弁当を習慣化すると、毎日の弁当作りや食事作りも非常に楽になります。
そして弁当・食事作りの時短が出来れば自分の趣味の時間も増え、毎日が楽しくなり、何より家族の健康維持にも貢献できます。無理をしないでマイペースで作り置きおかずを利用して弁当作りを楽しみましょう。

























